

大分県臼杵市は瀬戸内海に面しているが、その一部である野津町は内陸である。山林と畑の多いところで、どちらかといえば九州の中心阿蘇寄りだ。日当たりが良い山道を少し登ると増田一之さんと妻の由希子さんが大切に守っているキウイ農園がある。愛犬のクマスが軽トラックを降りた二人を先導するように畑へ駆けて行った。葡萄畑のようにキウイの棚が遠くまで続いている。その棚は大人の頭ほどの高さである。だから農園では少し腰をかがめて歩く。増田さんが「これくらいの方が、手が届くから収穫しやすいんですよ」と言う。キウイは蔓(つる)性の植物だが、植えてから30年以上経っているので地上から伸びている蔓は木の幹のように太い。生命力に溢れた植物で、放っておくと蔓がどんどん伸びて藪のようになる。この農園は増田さんが丁寧に剪定をしているらしく、棚の厚さが一定で地面には木漏れ日のように陽光が差し込んでいる。そして、そこには幾種類もの草が生えている。実に心地よい空間で、ピクニックには最高の場所だ。おまけに3年前、増田夫妻がこの農園を受け継いでからは完全に無農薬栽培だという。だから、農園の草も土も食べられるほど安全なのである。そのことがまことに贅沢で気分が良い。しかし、60アールものキウイ農園を現在の状態にまで創り上げるのは容易ではなかった。体を使って働くことをいとわない増田さんだからこそ可能だったのだ。地下足袋を履いた増田さんは俊敏そうで、細い体はバネかムチのようだ。そんな彼がしゃがんで「最初、棚はこれくらいだったんですよ」と言う。小学校2年生の背の高さほどだ。夫妻が農園を引き継いだ時、所有者はかなり高齢だったのでキウイの手入れは行き届いてなかった。だから棚が下がってきていたのである。彼らが農園を再生することになってから、まず草を刈り、絡み合った蔓を剪定し、新たに購入した金属管を支柱にして棚を上げた。刈った草も蔓も葉も栄養となって現在の農園がある。夫妻は3回目の収穫を終えて一息ついたところだった。

由希子さんは、長靴を履いて首にタオルを巻いている。農家の女性が働く格好をしているのだが、どこかスマートな印象がある。クマスと散歩をするように歩いていた彼女が「まだあるね」と言った。静かなので声が届く。増田さんが棚を見上げて「けっこう取り残しがあるなあ」と言いながらキウイをもぎ始めた。なるほど、大きな葉に隠れてキウイがぶら下がっている。産毛が生えたような焦げ茶色の表皮は日光を受けて輝いている。見た目は地味な果物だが「おいしそう」と思う。好物なので、もいですぐに食べたいほどだ。その気持ちを見透かされたのか、増田さんから「食べられませんよ、まだ硬くて酸っぱいだけです」と声を掛けられた。だから、鳥などの被害もないそうなのである。動物達は見向きもしないというわけだ。そして、「追熟させることによって甘くなるんですよ」と言う。キウイもそのままにしておけば自然に熟すそうだ。しかし、それでは美味しくはならないと言うのである。収穫したキウイは冷蔵庫に摂氏1度で貯蔵する。そうすれば半年間、味は落ちない。出荷する時は、その分だけバナナと同じようにエチレンをあて、さらに追熟させて甘くするのだそうだ。僕が「キウイはビタミンが豊富で体にいいんですよね?」と訊ねると、増田さんは「どうですかねえ?」と応える。たしかにキウイそのものはそうなのだが、その多くは農薬や化学肥料を使っているので薦められないということらしいのだ。その点、彼は自分達が育てているキウイに自信を持っている。「目指すのは食べた人が元気になる食べ物ですね。安全で美味しいのはもちろんですけど、ちゃんとエネルギーとして作用するような、そんな野菜を作りたいんです」。冬になるとキウイの葉が落ちる。それから蔓を切る剪定をして、花が咲いたら受粉をさせ、実をつけたら摘果をする。そして秋になると実ったキウイを収穫する。たいへんな作業の連続だが、やりがいをもって取り組んでいる。しかし、夫妻は農業をやるために野津に来たわけではないそうなのである。
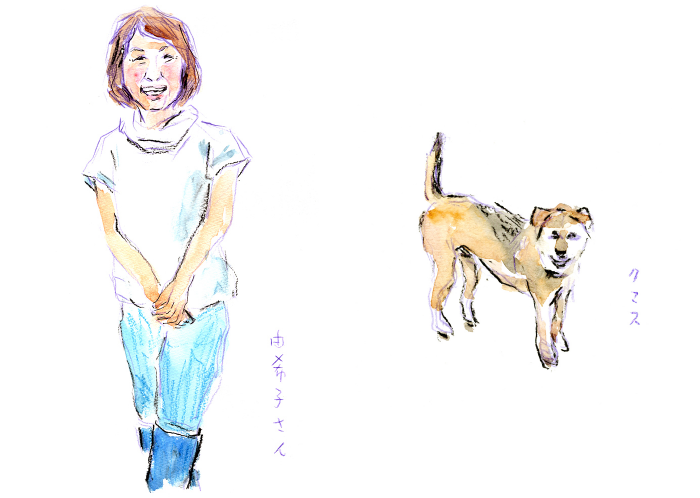
森に囲まれたキウイ農園を下って、二人が暮らす家を訪ねた。いかにも棟梁が建てたというような堂々たる日本建築だ。あたりは里の風景で開けてはいるが標高は高い。近所にも住宅はあるようだが視界にはない。目の前には山並みが遠くに見えるだけだ。家の横には鳥小屋があり、チャボと白い烏骨鶏がいた。納屋と、まだ新しいキウイの貯蔵庫があり、裏には畑が広がっている。そこを増田さんと歩いた。遠くの山との境には桃と無花果の農園があり、なにしろ広い。そこで大豆、小松菜、パクチー、ビーツ、ネギ、ジャガイモ、ナスなどを育てている。むろん農薬は使わない。ずいぶん歩くと農業用ハウスがある。「去年はメロンとトマトをやっていたんですけど、今年はアスパラで、収穫は来年からです」。ハウスの中にまだ細いアスパラが生えている。そして、銀杏より大きい白いものが地面に散らばっていた。「これは食用ホオズキっていう甘酸っぱいやつですね」。そう言いながら増田さんは、まだなっている実をとって僕に渡した。そして自分でも殻から小さな実を取り出して口に入れた。「うん、まだおいしい」と言って増田さんがほおばる。銀杏のように見えたのは提灯のような小さな袋で、その中にはミニトマトに似た実があった。味はトマトより甘い感じでけっこう旨い。僕は知らなかったが、食用ホオズキは鉄分が豊富で生活習慣病の予防や美肌効果もあるスーパーフードとして注目されているそうだ。
家に戻ると軒下の日陰に人参とパクチーが置かれていた。翌日のマルシェに出荷するそうだ。生姜に見えたのは菊芋だそうで、血糖値を下げる効果があるという。「スライスして油で炒めると美味しいですよ」と増田さんが言う。広い庭には日除けのテントが張られ、テーブルが置かれている。そこに由希子さんがお茶とキウイを出してくれた。その果実の断面は、愛想の無い見た目と違って華麗である。放射状の模様は万華鏡のようで、透明感のある緑色は翡翠に似ている。滲み出た水分が日差しを受けて輝くさまは水の宝石と言っていい。その宝石をほおばると「甘酸っぱい」が口の中に充満する。農園を見たばかりなので、その美味しさにありがたみさえ感じた。この頃は、黄色くて甘いキウイも売られているが、僕はこのキウイらしい甘酸っぱさが好きだ。水分を一杯に含んだキウイを平らげていると、増田さんが「皮も食べてみてくださいよ、皮の内側が美味しいんですけどね」と言う。輪切りにしたキウイのいくつかは皮がついたままだったが、それを剥いて食べていたのだった。勧められるままに皮を口に入れて噛んだ。由希子さんが「実と一緒に食べないと皮だけじゃ美味しくないですよねえ」と言って笑う。生まれて初めてキウイの皮を食べたが、食べられなくはない。増田さんが「ちょっと毛がありますから食べにくいですけどね、栄養が2倍あるんですよ」と言う。すると、由希子さんが「私は、やっぱり皮は剥(む)いた方が好き」と言ってまた笑った。

二人は同い年で、44歳だそうだ。誕生日は2日違いだという。増田さんが1976年2月23日生まれで由希子さんが25日生まれ。増田さんが「だから結婚記念日は2月24日にしたんですよ」と言うと、由希子さんが「そんなこと言わなくていいよ」と言って笑った。増田さんが野津町に来たのは39歳の時で5年前のことである。由希子さんと出会ったのはその半月後で、ほぼ同じ時に生まれた二人は、それまで全く違う人生を生きてきた。
増田さんが生まれたのは静岡県の焼津市で、やはり子供時代から元気だったようだ。静岡県といえばサッカー王国で、増田さんも小学校2年生から始めた。『キャプテン翼』の世代で、「遊びもサッカー、ゲームもサッカーでサッカー漬けの毎日だった」そうだ。ポジションはフォワードだったというから俊足だったのだろう。焼津市の選抜にも選ばれ、中学3年生の時には川口能活選手と対戦したこともある。ちなみにその試合は1対0で負けたそうだ。将来は日本代表を夢見て「やっぱブラジルに行きたかった」そうだが、次第に現実を知るようになる。藤枝北高校に進学し、サッカー部に入ったが1年生の時に中退した。「まあ挫折したのかなあ、情報科学科ってところでコンピューターの勉強をするんですけど、それも自分は違うなと思って」辞めた。それから増田さんの自立人生が始まる。一人で家を出て静岡市に住んだ。昼間は働き、夕方から定時制高校に通い、夜はサッカーの日々。定時制高校の静岡代表としてサッカーの全国大会にも出場したそうだ。4年間で高校を卒業した後は上京し、不動産会社の営業、スキー場のアルバイト、軽トラックで物干し竿の販売など30以上の仕事を経験した。「その頃は、自分に合う仕事を探していたと思います、それと海外を旅したかったんです」。増田さんは、金を貯めてはヨーロッパやアジアを旅した。中南米はメキシコ、グアテマラ、ベリーズ、エルサルバドル、ニカラグア、ホンジュラスを巡った。ホンジュラスは、世界で一番殺人事件が多く「わずか10ドルぐらいで人を殺す」そうだ。「そうですね、お金の問題ですね、根本はやはり貧困だと思いますよ」。増田さんの場合、根性が無くて仕事を転々とし、放浪を繰り返していたのではないようだ。どうやら大きな成功を夢見て好機を探していたようなのである。「それはありましたね、20代の頃は。海外に行って日本にない何かを見たり感じ取ったりして、そのうちに自分の経験が融合してパカッとなにかが開くんじゃないかっていう期待があったと思います。そのなにかを求めて彷徨って・・・みたいな」。やがて、求め続けた甲斐があって、「パカッ」の出会いが訪れる。
30歳になる頃、オーストラリアでは回転寿司の店で寿司を握っていた。そこで「庭の仕事みたいなのがあるんだなあ」と知った。「オーストラリアで日本の美に目覚めたというより、自然が好きなことと、子どもの頃からサッカーの他に、ものを創ることが好きだったことを思い出したんですよ」。増田さんは造園家になることを決心した。目指すものが見つかれば行動は早い。日本に帰って来てから浅草にある専門学校で庭のデザインを学び、卒業後は浜松の職業訓練学校に通って造園を学んだ。その後が面白い。彼は庭の本場ともいえる京都に行き、毎日庭をスケッチしていたというのである。夜はホテルで働きながら、朝になると自転車で京都各地の庭を訪ねては観察した。その数、150か所。その後、東京の庭園設計事務所で働いて埼玉県で独立した。西武ドームのガーデンショーなどに参加すると仕事の依頼があった。その時目指していたのは洗練されたデザイン。仕事は順調だった。
その頃から自然に関心があり、食べることを大切にしていたので有機野菜とか無農薬の野菜を買っていた。そのうち自然農法の学校に通い始め、畑を借りて野菜を自分で作るようになった。すると、だんだん面白くなってきて、さらに野菜作りだけでなくゴミが出ない循環型の方法を生活に取り入れたいと思うようになった。自分なりに勉強を続けていると『パーマカルチャー』というタスマニア生まれの農的暮らしを勧める思想に出会った。増田さんは、次第にそれを実践しないではいられなくなった。そして、とうとう埼玉の家を引き払って理想の土地を探し求める旅に出た。軽トラックを寝泊まりができるように改造して和歌山県、岡山県、熊本県を巡った。ついには熊本県の菊池市に半年滞在して良い土地を見つけた。そこを買うつもりで、いったん故郷の焼津に戻った。帰省している時、たまたま大分県の空き家バンク情報を見ていたら野津の家を見つけた。それで「ちょっと見てみよう」とやって来た。そして、日当たりが良かったことと、「あとは勘」でここへの移住を決めたのである。 その時は、野津で農業をやる考えは全くなかった。「農業ほど儲からない仕事はないと思っていた」からだ。新天地では自分が食べる野菜を育て、極力ゴミを出さない循環型の生活をしながら、仕事はあくまでも造園業をやるつもりでいたのだった。
由希子さんは、東京で生まれ、都内の団地で育った。3人兄弟の真ん中で「10歳くらいから精神的に変だった」と言う。「全然そんな風には見えないですけどね?」と言うと、「頑張ってます」と応えて笑う。増田さんが「感覚が人より敏感なんだと思う」と援護する。高校時代は「ちょっとアナーキーで、今思えばよく生きていましたよ」と振り返る。繊細でもろく、彼女はやっとの思いで生きてきたようだ。行動力があって、生きる力が旺盛な増田さんとは全く対称的な人生だ。20代半ばで「腹をくくって」精神科に通い始めた。そこで良い先生に出会い、薬に依存することもなく2年ちょっとで暗闇から抜け出した。といっても頑丈になったわけではない。自分の心と体との付き合い方を覚えただけだ。アトピーや喘息もあるので食べ物にも気を遣っていた。穏やかな生活を心がけ、マクロビオティックや菜食に関わる仕事をしていた。体が日光に弱く、虫に過剰に反応するので、まさか農業の道は考えたこともなかったが、空気のきれいな田舎への憧れはあった。そのうちに3.11が起こった。それもきっかけで翌年、熊本県にやってきた。将来は家族の移住も見据えて、まず由希子さんが、九州に暮らしの基盤を作るつもりでいたのである。阿蘇の旅館で働いていると体調はずいぶんよくなった。
5年前、増田さんが一人で野津に来て、まずしたことは家の片づけである。移住から半月後。なるべくゴミを出さないことを信条にしている彼は「不要な座布団や食器があって、誰か使う人がいないかなと思って」呼びかけた。すると、阿蘇で会ったことのある女性たちが受け取りに来た。彼女達は増田さんが一人暮らしなのを知り、由希子さんを紹介した。二人が最初に会ったのは阿蘇市のジョイフルだそうだ。次に二人は臼杵市で会った。運命というものはわからない。増田さんが野津にやって来たのは由希子さんと出会うためだったかもしれないのだ。そして、由希子さんが東京から阿蘇にやって来たのは増田さんに出会うためだったのかもしれない。わずか2日違いで生まれて別々の時を過ごしてきた二人は半年後に結婚した。
「友達は好きな仕事をしたり、外国に行ったりしていた、けど私にはできなかった。その気持ちがずーっとあって、彼は、それを全部やって来た人だからすごく嬉しかった。けど、ちょっと悔しいような変な感じ。でも、一緒に暮らし始めてから体が良くなりました。たぶん水が良いんだと思う、それと空気が東京とは全然違う」。安全な野菜も効果的だったかもしれない。由希子さんのアトピーや喘息はほとんどないほど軽くなった。動物も受けつけられなかったが、今はクマスと一緒にいても平気だ。「たまに東京に帰っても、その日のうちに、野津に帰って夕日を見ながら散歩したい!って思いますもん」。この土地が由希子さんの命を救ったのだ。それとなにより増田さんの存在が大きい。「結婚とかは別にしなくてもいいって感じなんですけども、彼のことは、やっぱり・・・・やっと出会ったんだな、って感じです、時間がかかりましたけど」。

増田さんは、16歳から自分のするべきことを探し始めた。それから長い間、世界を彷徨い、ついにオーストラリアで焦点が定まって造園の道を見つけた。それから学校に通い、現場で修行して独立し、やっと軌道に乗ったところだった。野津に移住してからも続けるつもりだった。しかし、由希子さんと出会い、家を二人で改築し、野菜を育てているうちに時間が経った。それは、夢を捨てたのではなく、野津での暮らしに理想を見つけたということだろう。一方、由希子さんは、東京で危うい人生を送ってきた。九州の自然が彼女の体と心を癒し、そして増田さんとの出会いが彼女の生命を強いものにした。二人が野津で暮らし始めて二年が過ぎた頃のことである。臼杵市役所に行った時、職員から「キウイをやりませんか?農園が広すぎて誰もやる人がおらんのです」と言われた。二人は決心して自分たちのキウイを作り始めた。そして、野菜の販売も始めた。今では加工品のドライキウイやキウイソースも製造している。これまでの経験を生かした二人の新たな旅が始まったのである。それまでは別々に旅をしてきたが、二人には共通点がある。それは、嘘が吐けない正直者だということだ。だから、増田さんは時間をかけて自分が完全に納得する道を見つけようとしてきたし、由希子さんは、それゆえに戸惑うことが多く、傷つきやすかったのだろう。そんな正直者の二人が育てるキウイや野菜に誤魔化しがあるはずがない。彼らは信用できる。増田さんと由希子さんは誰より命の大切さを知っているからである。そんな二人が野津の大地で育んでいるのは生命そのものである。夫妻はこれからも丁寧な仕事を続けて行くことだろう。
日が傾いて庭の大きな柿の木がシルエットになってきた。雑種犬のクマスが大きく口を開けている。その表情は、二人の顔を見上げながら微笑んでいるように見えた。
( 絵・文 二宮圭一 )
